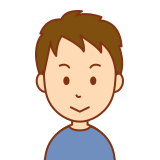
一本橋すぐに落ちてしまうな・・・
そんなに粘れないな。
なんかコツないのかな・・
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
・なぜ一本橋を行うのか
・一本橋のコツ、気を付けること
・試験でやってはいけないこと
・まとめ
この記事を書いている私は、指導員歴7年ほど。多くの教習生を指導してきました。どの課題も最初はできなくて何も問題ありません。練習をこなしていけばできるようになりますので、安心してくださいね。
なぜ一本橋を行うのか
幅30cm、長さ15m、高さ5cmの橋の上を渡っていきます。一本橋を行うことで以下のことが身につきます。
・姿勢の取り方
・目線の取り方
・低速時の安定した走行
狭い道を通る時やスピードが遅い時のバランスの取り方を身につけます。低速時のバランス感覚、低速時に使用する断続クラッチもマスターしていきます。
目標タイム
・小型二輪5秒以上
・普通二輪7秒以上
・大型二輪10秒以上
交差点を回る時や狭い道、あとはショッピングモールなどの駐車場にバイクを駐める時も低速は求められますよね。普通二輪をお持ちの方で大型二輪を取得しようと入校すると、まずこの一本橋で苦戦するでしょう。でも大丈夫です。普段の運転から見直し、交差点は徐行で回るようにまず心がけましょう。
一本橋のコツ、気を付けること


まず全教習生にお伝えしたいことがあります。
それは【タイムを気にせず渡りきること】です。
教習生の多くは「このタイムを出さないといけない」と考えてしまい、すぐに落ちてしまったり、怪我をしてしまう恐れがあります。なので最初は【タイムは気にせずに落ちずに渡りきること】を目標に教習に取り組んでいってもらえたらと思います。
✨一本橋のポイント✨
1.指定の位置の止め方に注意
一本橋の前に白いラインが引いてあります。教習所によってはサイドにパイロンが置いてあり、わかりやすくしていることもあるでしょう。その位置に止まった際のポジションに注目。コースに対して車体が真っ直ぐになるように持ってきましょう。教習生の多くはすでに斜めになっていたり、コースの端を狙うような位置に持ってきてしまう方が多いです。ローギアにするにも忘れないように。
2.スタート時の注意点
左足をステップに乗せるのは、バイクが動いて勢いがついてから乗せましょう。教習生の多くは、動き出す前に足を乗せる人が多いです。クラッチを開けてきて半クラッチからバイクが動き出しますが、そこまでラグがあります。クラッチを開けた瞬間に足を乗せてしまう人が多いので、自転車のように動き出して勢いがついてから乗せましょう。発進時アクセルを少し回してからクラッチを開けていきましょう。
3.最初の登る板に注目
計測板を登るため、少し衝撃が来ると思います。衝撃があることを頭に入れておきましょう。
4.乗った後の注意事項
乗ったら上体をやや前に傾けて、ニーグリップ(タンクを挟む)をする。ハンドルで少し左右に動かしてバランスをとりましょう。
試験でやってはいけないこと
緊張する卒業試験ですが何をやってはいけないのか気になりますよね。ここでは一本橋でやってはいけないことを解説していきます。
・一本橋から落ちたら失格
・エンストも失格
・転倒も失格
・タイム不足は減点
以上の点に注意が必要です。
まずはしっかり落ちずに渡り切ることを目標にしましょう。よくやってしまうのがタイムを気にして粘り続けてしまい、落ちてしまうことです・・・これはかなりもったいないこと。なので試験はあまりタイムは気にせず、いつもやっていることをやること。シンプルに考えましよう。
タイム不足は減点ですみます、2秒でいってくださいってわけではありません。背伸びせずに自分が今やっているベストを尽くしてくださいってことです。
まとめ
今回は一本橋の概要、コツ、気をつけるべきについて紹介してきました。
一本橋は、低速を求められるため、皆さんが難しいなと思うかもしれません。それでも心配ありません。いきなりできる人はいませんから、しっかり練習して一本橋をマスターしてみてください。






コメント